
|
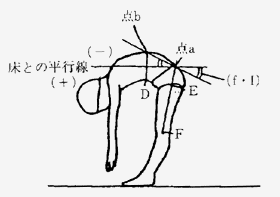
図2 脊柱屈曲角度(f・I).
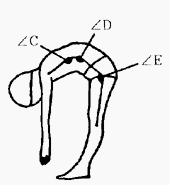
図3 脊柱屈曲角度(f・?U).
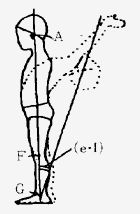
図4 脊柱伸展角度(e・I).
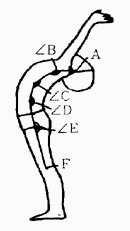
図5 脊柱伸展角度(e・II).
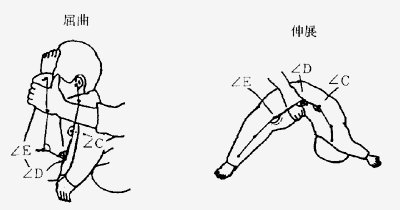
図6 乳児の測定方法(O〜2歳).
下の点とその点を結ぶ直線のなす交点の後面角(e・?U)を求めた。なお、乳児については仰臥位からの屈曲・伸展を補助し、基準点を求めた(図6参照)。 研究結果と考察
1. 脊柱可動域の「多角形」計測について
フィットネステストにおける脊柱屈伸の可動域測定は、これまで、(a)身体の基準軸と移動軸のなす角度、(b)基準軸上および移動軸上の点間の距離、(c)あるいは外部基準点(線)へのリーチ度や乖離度などによって計られてきた8,17)。また身体の基準点としては、大転子、腸骨陵、腸骨前上棟、第5腰椎、ヤコビー線、胸骨、肩峰、第7頸椎、顎、耳珠、頭頂などさまざまな部位が用いられてきた。 これら基準点は、円柱(錐)体をなすヒトの体幹部の、前額・矢状面のさまざまな位置にあるため、体格の異なる対象を比較したり、同一面上の変位としてとらえるには限界がある。また、角度法にせよ距離法にせよ、2軸間の変位は軸の直線性が高い部位には適しているが、体幹のような円柱弾性体の場合は、弯曲度や弯曲部位の特定ができないという限界がある。 本論に先立ち、同一資料を角度法、リーチ法などいくつかの方法で比較し、相互の相関や一致度を確かめた。たとえば、図7は2種の角度法で計った屈曲角の相関をしめしたものであるが、相関係数は中等度(r=0.51,P<0,001)となり、測定法によって結果に差のあることがわかる。とくに脊柱弯出部位に個人差・年齢差のあることが推察されたので、本論では、体軸の基準点を増やすという『多角形法』を新たに併用した。その特徴は次の点である。 a. 伸展・屈曲時の脊柱沓出部位の把握ができる。 b. 伸展・屈曲時の弯出部位を同一基準点でみることができる。 『単一角度法』と『多角形法』の関係をしめしたのが、図8,9である。まず屈曲角度についてみると(図8)、『単一角度f.I』と『多角形法f−?U』の『角C』『角E』にそれぞれ有意の相関があり、『角C』では正相関、つまり『単一角度』が硬いほ
前ページ 目次へ 次ページ
|

|